脳と心の断捨離カウンセリング「天香」のわたなべ じゅんです。
週末、大阪市内の音楽フェスがあった。
「納屋de cafe」メニューの、紫蘇ジュースとジンジャーエール、他フルーツジュース… ちょうど今どれも旬を迎え、作り終えたところだった。出品させていただくのは、二度目になる。(私は歌えません)



ここで会う人は、私が日常では関わることがほとんどない人たちばかり。
ラッパーさん、レゲエミュージシャン、ダンサー、DJ、映像の世界の人や、公園に遊びに来た老若男女。みんな自由に、自分らしく楽しんでいるように見えた。
主催者も、スタッフも、お客さんも、私が会うのは多くても二度目。
つまり、何のしがらみもない関係性の人たち。

店先に立っていると、「雨やんでよかったね~」とか、軽く身の上話をしてくれる人もいた。
ある男性が買いに来てくれた。
子供が二人いるが、離婚をしているとのこと。足元で遊んでいる私の孫を見て我が子のことを思い出したらしい。
でも、離婚してからの方が、前の奥さんや子供たちと、うまくいっていると、懐かしそうで優しくも、どこか切ない目で、話してくださった。
「子供を育てる女性は強い」そして自分は「バカ」だった。などと言っていた。
私も離婚を経験しているので、別れた夫のことが少し目に浮かんだ。そして私自身も若さとおごりで歩んだ半生を振り返りながら、ただ深く頷いていた。
不思議な感覚の時間旅行をしたのは、時間にして1~2分だったと思う。

大きなスピーカーからは、ラッパーが心の叫びを声にしていた。ファンの人たちも、肩や腰を揺らしながらそれに賛同していた。人にはみんな、その人だけのストーリーがある。
歌いながら、涙を流しながら、それでも明日が連れてくるわずかな希望を信じて生きている。
こんな私も、一時はシングルマザーで、おまけに親の保証債務を背負うことになり、働けど働けどお金はひたすら右から左に流れていくだけ。
自分から切り出した離婚であったが、子育てや生活の不安や責任感などで押しつぶされそうな日もあった。辛くとも泣いている暇はなかった。けれども幾度か耐え切れられず、ひとりシャワーに額を当てながら涙を流した。3階の窓から下を見下ろしたこともあった。でも、今、生きている。そして生きていてよかったと心から思う。
出口の見えない毎日でも、何も変わらなく見える毎日でも、昨日と同じ日はない。わずかでも必ず変化している。

今、月に一度、同じ志を持つ女性と、市の座談会をやっている。そこでは、めいめい自分が抱えている悩みなどを話す。家族や身近な人には逆に言いにくいことがある。友達にも言えることと言えないこともある。そんな悩みやモヤモヤを話すという場だ。ただ話すだけなのに、なんだか癒されるしスッキリする。次の日から何かが変わったという声も多い。
他人の失敗談や苦労話、経験談で癒されるのは、なぜ?
①学びと教訓を得られる
他人の失敗から学ぶことで、自分が同じ過ちを繰り返さずに済む
「賢者は歴史に学ぶ」という格言にも通じる考え方
<例>ある人が仕事での無理がたたって体調を崩した話を聞くことで,自分も働き方を見直すきっかけになる。
②共感とつながりを感じられる
苦労や失敗は誰にでもあるもの。そうした話を聞くことで、「自分だけじゃない」と感じ、孤独感が和らぐ
・精神的な安心感が生まれる。
・「完璧な人間はいない」と気づくことができる。
③自己理解や内省のヒントになる
他人の経験に照らして、自分の行動や考え方を見つめ直すことができる
・自分だったらどうするか?と考えるきっかけになる。
・自分の価値感や判断基準を深める手助けになる。
④逆境への耐性を高める(レジリエンスの向上)
苦労を乗り越えた人の話には、困難に立ち向かうヒントや勇気が詰まっている
・困難への心構えができる。
・持続力・忍耐力の強化。
⑤感謝や謙虚さが育まれる
他人の苦労を知ることで、今の自分の環境に感謝できたり,驕り(おごり)を戒めたりすることができる
⑥コミュニケーションの質が高まる
苦労話にはその人の本音や背景が込められているため、深い会話や信頼関係を築くチャンスになる
★聞き方の姿勢も大切
話を「上から目線で評価する」のではなく、「真摯に聞く・受け止める」姿勢が大切。
心理学的な視点でのメリットと意義
1,共感の発達:カールロジャースの来談者中心療法
・他人の苦しみに触れることで、感情的共感(感情レベルで同調する)と、認知共感(相手の立場を理解する力)が育まれる。
ロジャースは、「共感的理解」が人間関係の土台であり、癒しの鍵とした。
・苦労話を聞くことで「他人の視点から物事を見る」訓練が自然につく。
〇共感力が高まると、対人関係、信頼構築、自己理解にも好影響があります。
2,ナラティブ・セラピー(物語としての人生):マイケル・ホワイト、デイビット・エプストン
・人は自分の人生を「物語」として意味づけながら生きている。
・他人の苦労話を聞くことは、「別の視点からの物語」に触れること。
それにより、自分の人生のストーリーも見直され、新しい視点(再物語化/ re-authoring)が得られる。
〇他人の語りは、自己アイデンティティの修正や補強にもつながります。
3,社会的学習理論(観察による学習):アルバート・バンデューラ
・他人の経験を観察し、それを自分の行動に取り入れるというプロセス。
・成功だけでなく、「失敗から立ち直る様子」も、強力なモデリング(模範)になる。
・自分が失敗したときの対処法や考え方の参考になる。
〇他人の「トライ&エラー」を追体験することで、試行錯誤の幅が広がる。
4,自己開示と相互信頼の形成:ヨハリの窓
・他人が苦労や失敗を話す=「プライベートな情報の開示」
それを受け止めることで、「心理的安全性」や「信頼関係」が築かれる。
結果として、自分自身も安心して自己開示しやすくなる(相互的な深まり)。
〇苦労話の共有は、人間関係の「深さ」をつくる鍵となります。
5,レジリエンス(心の回復力)の強化:ポジティブ心理学(マーティン・セリグマンなど)
・他人の苦労話の中には、「どう乗り越えたか」「どう受け止めたか」という前向きな意味づけが含まれていることが多い。
それを聞くことで、困難=成長の機会という視点が養われ、自分の回復力も高まる。
〇苦労をどう意味づけるかが、精神的な柔軟性を決定づけます。
まとめ
他人の失敗談や苦労話、経験談を聞くことは、単に「情報を得る」だけではなく、
自己成長・共感力・対人関係・内省・回復力のすべてに働きかける非常に深い心理的プロセスと言える。
心理学的に表現すると、少し冷めてしまう気もするが、人は人に傷つき、人に癒されるということだろうか。
「人の不幸は蜜の味」などという言葉もあるが、「蜜」で自分の心が虫歯のようになってしまわないよう、それが、勇気と希望と成長に変えることが出来たらいいと思う。

ここまでお読みくださり、ありがとうございました。

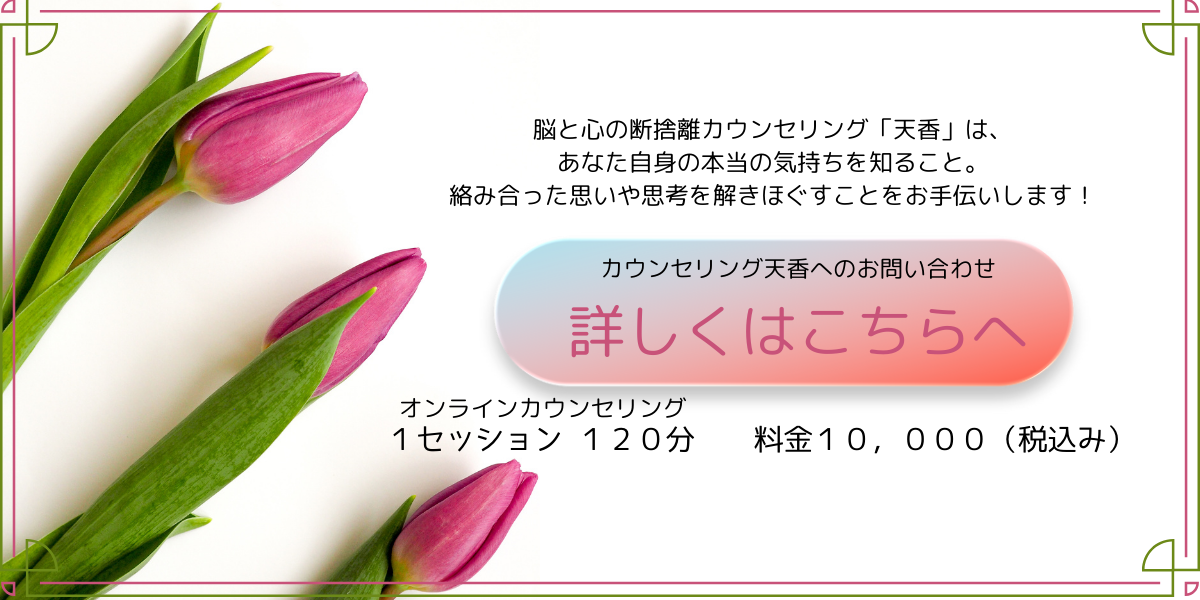


コメント