脳と心の断捨離カウンセリング「天香」のわたなべ じゅんです。
「せっかく住んでいる地域で開催されるのだから」と、向かった「万博」。
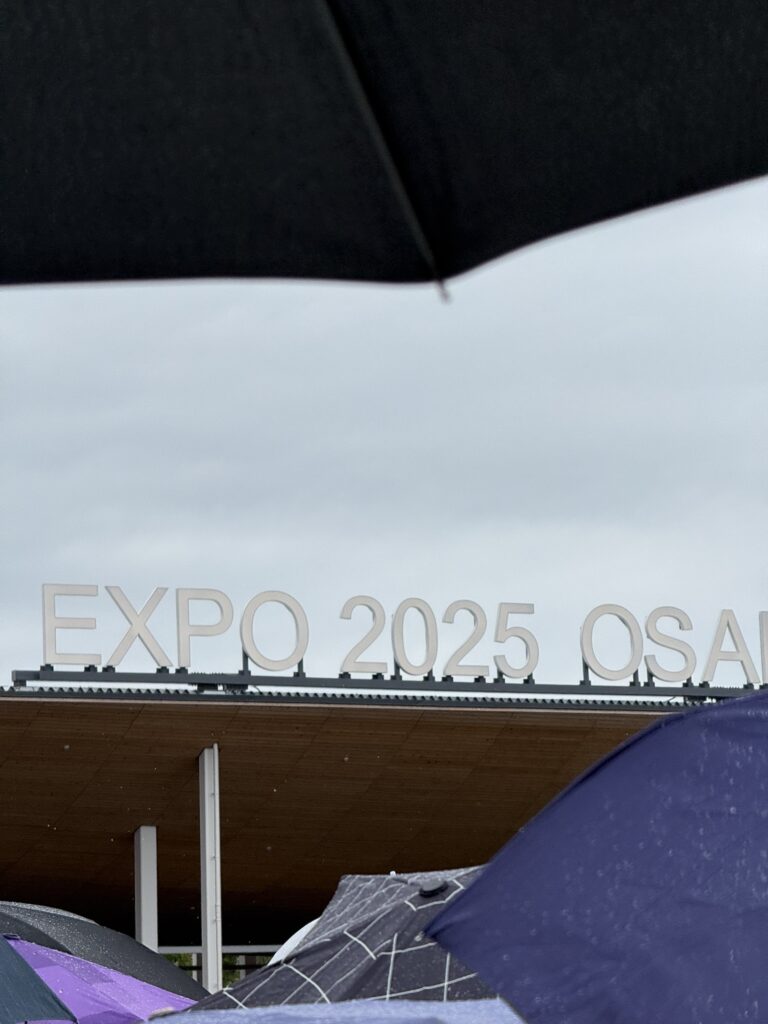
実はこの私、この手のものが「楽しめない」タイプなのです。
大阪ではUSJ(ユニバーサルスタジオ)がある。
関東には、ディズニーランドがあります。
行ったことはあるけれど、心底楽しめないという残念な性分でありました。
万博には、すでに数回行っている友人がいる。
彼女は、私からするとテーマパークの達人。
今回は、色んな豆知識を授けてもらい、初めて来場するのに、効率的に楽しめる情報をいただいた。
まず、並ぶのは東ゲートだったが、向かって左端が早いとのこと。
たしかに、他の列に比べると、列の流れが速く、スムーズ。
この時期、雨が降ったり止んだりの不安定な天候ということもあり、傘は「折りたたみ傘」が便利。実際、本当に降ったり止んだりで、小さなビニール製のバックがあれば、傘をさっと出したり、しまったり、日傘兼用だったら一石二鳥で便利だった。

ゲートをくぐると、様々なパビリオンが目に飛び込んでくるけれど、どこが列の最後尾なのかを探すのが大変なほど、人が蛇のようにグルグルと並んでいる。
行き当たりばったりで行くよりは、少し興味のある国があるなら、下調べしておいた方がと良かったと思った。
例えば、「フランス館」では、パンとレストランとパビリオンの3つに列がわかれている。「フランスだ!」と、ただただ並んでしまったら、順番が近づいてから、入りたかったものとは違う、パンの列に並んでしまっていた?! ということもあるようだ。しっかり、希望の列に並ぶように気を付けたい。
それから、喫煙者は、喫煙コーナーが館内にはない。東ゲートの外にだけあるので、いったん出口で再入場のスタンプを手に押してもらい、再入場となる。
万博会場の西と東では、歩いて20分ほどかかるため、生きたいパビリオンと喫煙タイムのスケジュールを組んでおいた方が良いかもしれない。東や西に、行ったり来たりしては、並ぶ時間も含めて、移動だけで疲れてしまう。
ちなみに私は、ミャクミャク君とサンリオのコラボ商品を買ってきてほしいと人に頼まれていたが、どこも売り切れだった。夕方からは、比較的入りやすかったお店だったが、午前中はグッズストアも90分以上待ちの列だった。何にどのくらい時間を費やすのかは、ある程度優先順位を考えていた方がいいようだ。
世界の国々の、文化や歴史を、写真や映像だけでなく、その国の人を通じて触れることができ、未来体験もでき、面白かった。
ただ、「さぁ、楽しめるぞ!」と思ったのは、抽選で予約が出来ていたパビリオンの見学がすべて終わった16時すぎの時点だった。
列に並んでいる間、他のパビリオンの予約やキャンセル待ち情報を調べたりする時間が多かった。あらかじめ、携帯電話のバッテリーが早く無くなることを教えられていて、「そんなに使うの?」と疑問に思っていたが、実際やはり充電が減るのはいつもより早かった。
会場の地図をプリントアウトして持参していたが、次のパビリオンまでの距離や場所や所要時間を検索するのにもスマホは役立った。(専用のアプリもある)
比較的効率よくは回ることはできたものの、「楽しむ」よりも「タスク」に変わっている部分があることに気がついた。
そうか!これだ。
私がシングルマザーで子育てをしていたころ、このようなところに子供たちを連れていくことが、少々義務的観念に縛られていたことを体が思い出させた。
「ディズニーランド」のお土産をいただくたびに…
「家族旅行」のお土産をいただくたびに…
なんだか、いただいてばかりで、うちの子たちはそんなに連れて行ってはあげられていない…。
そして、半分は親の務めのような気持で旅行のスケジュールを組み立て、我が子を犠牲にしてきたものだった。親が楽しめていないのに、子ども達が楽しめたはずがない。気の毒なことをしたものだ。
万博を効率よく、楽しめる豆知識を授けてくれた彼女は、パビリオンを楽しむ達人だ。
一方私は、楽しむことが苦手だということを話した。
すると彼女は、田舎育ちで煌びやかなものに憧れてきたので、大阪の繁華街でもわくわくすると言った。人の多い所よりも、少ない所に足が向かう私とは真逆だ。
それでも、同じ行くならば、「楽しめる」ほうがいい!
万博は、ディズニーランドと比べると〈ある視点では)面白くないと思う。当たり前だ。テーマパークではない。
ある意味、万博だって未来の地球を垣間見ることができる夢の世界だが、おとぎの国ではない。
未来を考え、命を考え、地球全体を考えるきっかけになるような場所であった。
「楽しめる」or「楽しめない」は、「好き」or「嫌い」があるように、それぞれだし自由だと思うが「楽しむこと」が得意じゃなかった私が参考にしたことがある↓
ナラティブ・セラピーという考え方で、ものごとを見る
ナラティブ・セラピーの基本的な考え方とは
1.人は物語によって自分を理解する。
例:同じ出来事(失恋・退職など)でも、「私はダメな人間だ」と語るか、「大きな学びだった」と語るかで、その人の心の状態や未来の選択が変わる。
2.問題は人ではなく、問題は問題である。
・「あなたがダメなのではなく、問題があなたに語り掛けている物語が、あなたを縛っている」
・「自分=問題」と思い込んでしまっている状態を「語りの構造」に着目してほぐしていく。
3、外在化
・問題を「自分の一部」ではなく、「自分の外にあるもの」として捉えなおす。
例:「私は不安な人間だ」→「不安」が時々私の中に入り込んでくる。と捉える。
4,再物語化(再ナラティブ化)
・染みついてしまっている固定化された「苦しい物語」を問い直し、別の視点から語り直すことで、新しい自己像・希望の物語を作っていく過程。
例:「私は人に迷惑ばかりかけてきた」→「困ったときには周囲に支えてもらえる関係を築いてきた」
5,別のストーリーの発掘
・苦しみの物語の中にも、実は「希望」「強さ」「価値」が隠れていることが多い。
過去の出来事をストーリーとして語ることで、その小さな証拠を探し出し、新しい物語の種にしていく。
人の記憶というものは、曖昧だ。
自分の考えに基づいて都合よくストーリーを作る生き物だと思う。
その修正をうまく活かして、さらに幸運を引き寄せれる体質にしたいものだと思う。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

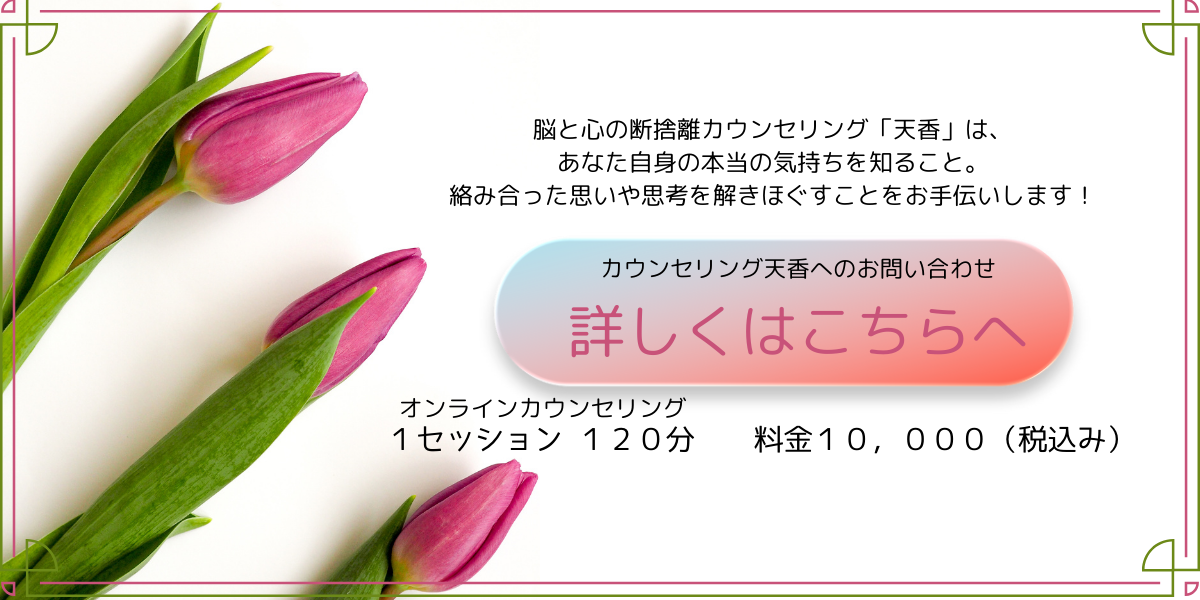


コメント